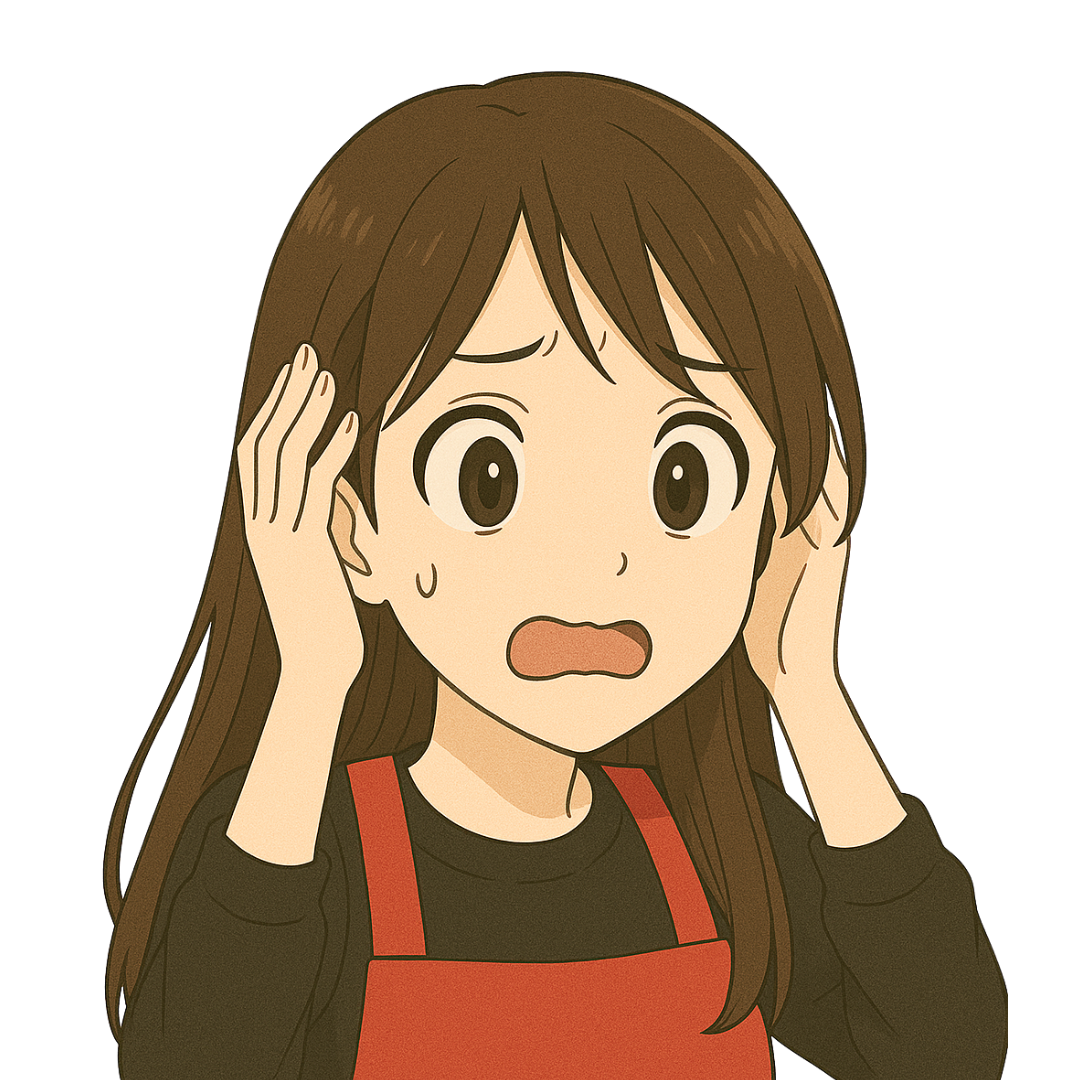
ご自身も不登校を経験されたなら、お子さんが不登校になっても大丈夫だったんじゃないんですか?
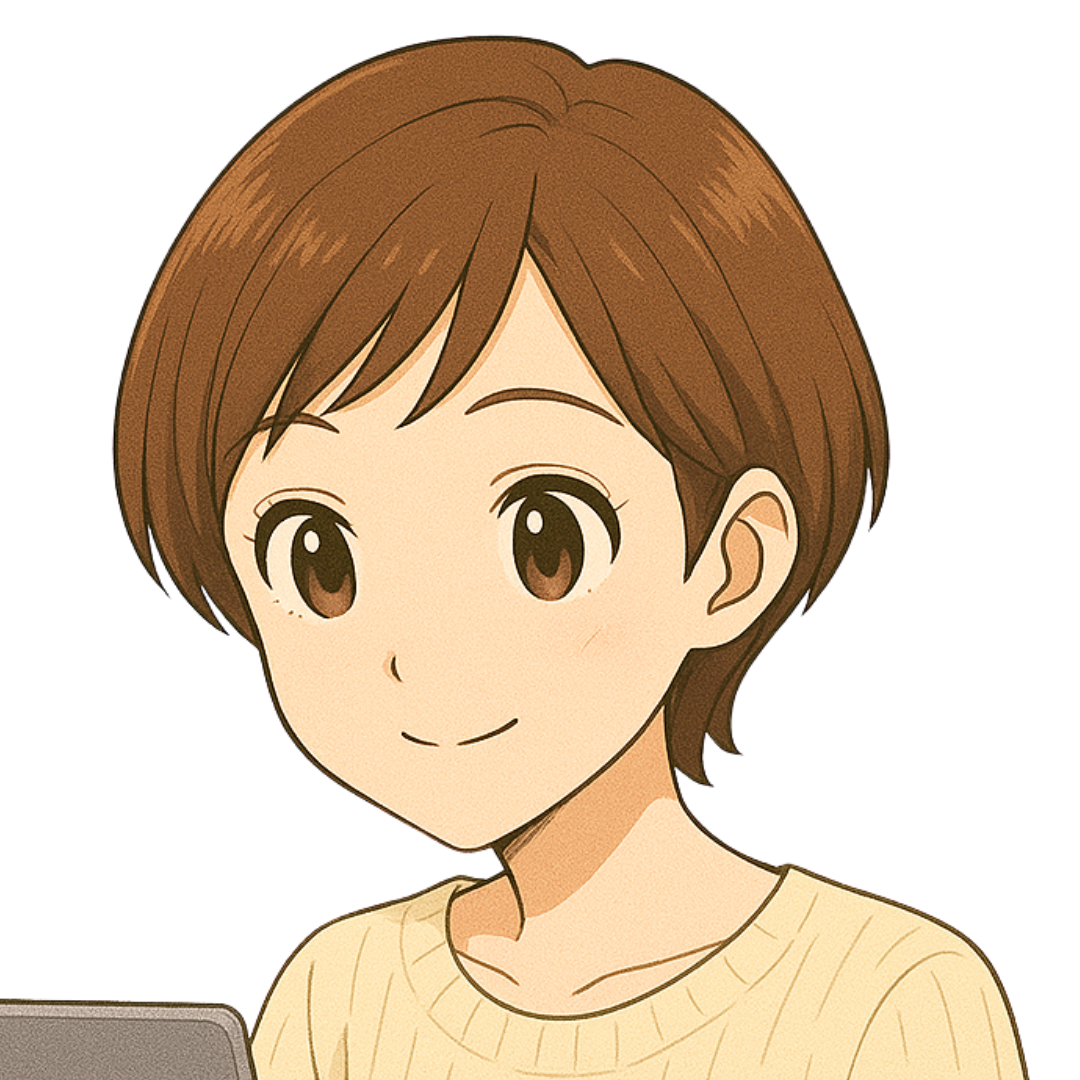
いえいえ、全然そんなことなかったです。
娘が学校に行けなくなったとき、実は私もすごく悩みました。
「どうして行けないの?」「何が悪かったの?」って毎日検索して…。
前の記事でも書きましたが、小6の娘は小1から不登校です。
そして、そんな母である私も、小学校から高校まで不登校でした。
「親も不登校を経験していたなら、子どもが不登校になっても落ち着いて対応できるんじゃない?」
そう思われることもありますが、実際はまったく逆でした。
不登校経験者だからといって、我が子が不登校になったときに「大丈夫!」と言ってあげられる自信は、私には当初ありませんでした。
本気で悩んで、辛くて、泣いた日もあります。
大人げないことに、まだ7歳だった娘に泣きながら本音をぶちまけてしまったこともありました。
でも、その経験を通してひとつ気づいたことがあります。
それが「不登校の原因を探すより、まず“子どもの安心”を作ること」 だったのです。
娘が学校に行けなくなった朝
娘が初めて「行きたくない」と泣いたのは、小学1年生の冬。
熱もないのにお腹が痛いと言い、朝になると必ず泣く。
体調が悪いのかと心配して休ませると、昼間にはケロッと元気になっている。
最初は体調不良だと思い、病院にも通いました。
でも結果は「異常なし」。
「行きたくない」と言われても理由が分からず、私は毎朝「どうして?」「行けば楽しいよ」と言っては泣かせてしまいました。
今思えば、あの頃の私は「娘を助けたい」という気持ちより、「私が仕事に行くために、学校へ行かせなきゃ!」という焦りに支配されていました。
「学校に行きたくない」の中にあった、見えないSOS
娘は小さい頃から、少し「こだわりが強い子」でした。
・服のタグがかゆいと泣いて着替えられない
・大きな音が苦手で、運動会では耳をふさぐ
・グループ行動が苦手で、友達の輪に入りづらい
でも当時は、それを「性格」だと思っていました。
ただの「繊細な子」「神経質な子」だと。
でも、本当は違ったんです。
娘にとって学校は、音・におい・人の多さなど、あらゆる刺激がしんどい場所だったのです。
発達外来でわかった「ASDという特性」
謎の体調不良が続き、小児科の医師の紹介で発達外来を受診しました。
正直、最初はショックでした。
「うちの子が発達障害…?」と頭が真っ白になりました。
検査の結果、娘は軽度の自閉症スペクトラム障害(ASD)でした。
医師からこう言われました。
「この子は、人よりも感覚が敏感で、変化にとてもストレスを感じやすいです」
その言葉を聞いた瞬間、涙が止まりませんでした。
やっと何か「答え」を見つけられた気がして…。
娘の「学校に行きたくない」は甘えじゃなく、逆に頑張りすぎていたSOSだったんです。
解決策は「学校に戻す」ことではなかった
それから私は、「学校に戻す」ことをやめました。
代わりに、「安心できる毎日を作る」ことを意識しました。
・朝、無理に起こさない
・家で過ごす時間を穏やかにする
・好きなこと(絵や音楽)に集中させる
・“頑張らなくていい”空気をつくる
すると、娘の笑顔が少しずつ戻ってきたんです。
…とは言え、「学校に行かなくても大丈夫」と言えるようになるまでは私でも時間がかかりました。
甘やかしじゃないの?
仕事はどうするの?
上司は事情を知っているけど、娘を連れて出勤したいなんて言っていいの?
本当に学校に行かなくて大丈夫?
などなど。
いくつもの葛藤を越えて、今「ママも学校に行ってないし、大丈夫」と言えるようになりました。
まとめ:焦らず、「理解」から始めよう
発達特性の有無に関わらず、子どもは大人が思っている以上に「自分の気持ちを言葉にする」ことが難しいそうです。
(これは、あとから精神科の先生に教えてもらいました)
ときには、本人ですら「なぜ学校に行けないのか」「何がつらいのか」が分からない場合もあります。
そんな中で、大人が一方的に「何がイヤなの?」「どうして行かないの?」と問い詰めてしまうと、子どもはますます自分の気持ちが分からなくなってしまうんですよね。
だから私は、“原因を探す”よりも“安心できる空気を作る”ことを意識するようになりました。
子どもが自分の気持ちを言葉にできるようになるのは、「安心できる」「否定されない」と分かってから。
焦らず、その日その日の「できたこと」「笑えた瞬間」を大切にしていきたい。
そう思っています。

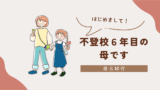

コメント